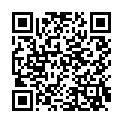会報一覧(第12号)
__RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY__の
/chibunken/works/2012_detail/id=45__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__/chibunken/works/2012_detail/id=47__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__/chibunken/works/2012_detail/id=48__RCM...
【伝統芸能文化の振興シンポジウム ~繋げたい!桶川の伝統芸能~】 平成25年2月3日、伝統芸能文化の振興シンポジュウムを市内のさいたま文学館文学ホールにて開催した。
シンポジュウムの主題は『伝統芸能の現状と役割』と称し、桶川の伝統芸能のささら獅子舞の2団体の代表者と檜枝岐歌舞伎座長を加えた3名のパネラーにより行われた。
シンポジュウムの終了後、檜枝岐村の自然や四季の暮らしや伝統芸能を描いたドキュメント映画、『やるべえや』を上映した。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 平成24年6月19日、小川会長と桶川小学校を訪れる機会があった。校門の正面を入ると左側に、統合により元・南小学校から移設された二宮金次郎像が聳えている。私は以前から、この像が建立された時代は金属不足で“コンクリート製だ”と、少し軽く思っていた。
「ちょっと風化しているが、間違いなく御影石製だ」と小川会長に教えられ、よく観ると確かに白い御影石製の像だった。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 桶川市坂田の加藤農園の入口に大宮競馬の記念碑がかつてあった。高さ2.5m幅1.2mの立派な碑であった。現在、この碑はさいたま市北区の区役所敷地内の公用車駐車場内の植込の中にある。平成20年の区役所庁舎の設置に伴い桶川から移設したものであろう。私がこの碑に気付いたのは昭和56年以降であるが、どうして、桶川に大宮競馬の記念碑があるのかという謎であった。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 3年前から「縄文の食文化を知る」と銘打って栃餅作りを桶川地域文化研究会の仲間数人とやってきた。栃の実は非常にアクが強くてそのままでは食料にならない、でも縄文人は水で晒して喰っていたという。もっとも彼岸花の球根などは毒性が強いが、それさえも毒抜きをして喰っていたというからそれに比べたら大したことではないとも思えた、栃の実は毒ではない、えぐいだけだ。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 平成24年度の中間全体会は、平成24年7月1日(日曜日)に、桶川公民館3階の大研修室において開催され、午後2時より研修会を行った。研修は、篠津の由緒ある神社の祠(し)掌(しょう)(管理、宮司・総代・氏子の橋渡しの役割を担う)の家に嫁いできた金田節子氏に「多気比売神社と共にある暮らし」と題して講演していただいた。ここでは、その概要を報告する。
多気比売神社は地元では安産、子授けの神様として「姫宮(ひめみや)様(さま)」と親しみをこめて呼ばれる大変由緒ある神社です。延喜式神名帳に記載された神社で、桶川では最も由緒のある神社です。お話は、パソコンによる画像を見ながらのお話となりました。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 1945年(昭和20年)8月15日、日本の戦争は終わった。戦闘帽、軍靴に巻脚絆、学徒動員で陸軍大宮造兵廠の旋盤工だった少年(旧制中学5年生)であった私は、その日、午前中に帰され、昭和天皇のご詔勅を自宅で拝聴した。その後は、何が何やら見当もつかず、すべて成り行きに従う生活を続けるより仕方なかった。
9月にD・マッカーサーが厚木飛行場に飛来した。連合軍総司令部(GHQ)の日本国占領がはじまった。そして、何とここ桶川の三井精機の工場にもアメリカ第7騎兵師団の一部が進駐してきたのだ。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 厳しい暑さの8月15日、12時に大事な放送があるということで家中が緊張していた。その日は父が役場に出勤していて、兄は出征中。家に残されたものは祖母と母、長姉と女学生の姉2人と、小学生の私に4歳の妹の女ばかりの7人。それに手伝いの夫婦者と畑を手伝う男衆、隣のおばさんなど大勢がラジオのある部屋に集り玉音放送を待った。
詳しいことは理解できないが、子どもながらに「その時が来た」という緊迫感は伝わった。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 昨年(平成24年)秋、川越市立美術館にて秩父(皆野)出身でS市柏原ニュ-ウタウン在住の方の個展を参観した。作品で入間川河原・堰・近隣公園・秩父山麓等の光景を見て自分の入学前幼児期のことをとても懐かしく思い出した。
小学校に入学する前の記憶であるので大分大昔のことである。県西部地区の田舎に生まれた。戦後間もなくのことで10年も経ってない時期なので世の中がまだ落ち着かない時であったと思う。物資も欠乏していたと思う。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ さいたま市岩槻区の小溝という集落に長命寺という天台宗の寺があります(天台宗、板東札所第12番慈恩寺の近く)。この寺のことを知ったのは今から50年も前のことで、当時、浦和通信制高校で勉強をしていた時この寺のすぐ近くに学友がおり「うちの家の近くに長命寺という寺があって、この寺の先代の住職は川田谷の出身で内田姓の人である」ということを聞いた。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ さて、何の土器を作ろうかな!あと三日で北海道への車旅。当分帰ってこないし、時間もないから簡単な土器にしようと資料を見ていると,何故か山形県西ノ前遺跡の「縄文の女神(ヴィーナス)」と、長野県中ツ原遺跡の「仮面の女神(ヴィーナス)が眼に留まった。
縄文のヴィーナスは八頭身美人で、長い脚にパンタロンルックであり、顔には細工がしていないが、何か微笑んでいる様で優美である。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ この碑は、「下の寺」と呼ばれている浄念寺の山門をくぐった右手に所在する桶川宿の開闢を示す唯一の金石文である。碑面に「浄徳院殿天翁梵長大居士」「薬師如来聖徳太子作」「東麟院殿元彩祥鳳大居士」の文字が三行で刻まれる。裏面上部に円形の穴が穿たれる。左右の枠縁に以下の開闢に係る銘文が確認されるが、追刻の可能性もある。
「慶長十一丙午八月二十六日」(右)__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 第1回は山梨の縄文文化、古墳文化、浅間信仰、第2回は、信州の古墳文化、終戦末期の国家的防空壕施設の巡検を実施した。今年度は、東京、神奈川で、現代史の遺跡を主とした。平成24年6月10日に実施し、小型バス1台で、天候は晴れ、当日の参加人員25人であった。以下、訪問した施設毎に概要を記し報告としたい。
調布飛行場(掩体壕)__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__ 伝説の古刹を、たどりながら、群馬県境までを目指す。
中山道、深谷宿から本庄宿まで2里25町(11km)の道中“ぶらり歩き旅”を続けます。
深谷宿、北はずれ萱場稲荷神社周辺を通過すると道は右に蛇行、宿根で、新道と合流するが突き抜け、新道と平行しながら岡部南で再び合流し岡部町へ入ります。岡部町は阿部氏(江戸初期岡部の領主)ゆかりの源勝院や、岡部六弥太(鎌倉武士)が眠る普済寺など、由緒ある古刹が数多く、集まる地域です。__RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY__
おけがわライフイベントカレンダー