『和宮下向と桶川宿』講演を聞いて
2012/03/31
ここでは、平成22年7月3日(日)に、勤労福祉会館において行われた県立文書館に勤務されている宮澤好春先生のお話しを聞かせていただきましたので、その感想を紹介させていただきます。講演の副題には「庶民からみた和宮下向」とあり、県文書館の先生の話に、身近なものなのかなあとの思いがありましたので、久し振りに学校の授業を受けているような感じで、ジッと聞く態度になりました。
宿場の基本的な流通制度としての問屋とそこに配備が義務付けられていた人足50人と馬50匹の配備があり、これは通常の輸送のためのものだった。あの大藩の加賀藩では2,500人、和宮の通行では4万もの大きな通行と言われ、当然、島崎藤村の小説「夜明前」に描かれてたように常時配置の人数では無理であり、この通行を助ける制度として助郷が指定されていたという。この“助郷”の説明から大名達の街道通過のための荷物の運搬に、自分達の生活や仕事におかまいなしにかり出され、いかに大変だったかなどの説明がありました。
そして中山道の特徴として、大名達の参勤交代による通行の他に、10代徳川家治に嫁した五十宮、12代徳川家慶に嫁した楽宮、13代徳川家定に嫁した有姫と寿明姫、そして14代徳川家茂嫁した和宮など多くの姫たちがこの道を通って江戸に来たことから“姫街道”と呼ばれたという。他の街道に比較しその割合が多く、それは優雅な華やいだ響きをもつような道に思えるが、その運搬のすべてが庶民の肩に重くのしかかり、生活を圧迫していったということをお聞きし、何か複雑な思いを感じました。この助郷は桶川宿に割り当てられている村々が37ヶ村にも及び、多くの村人達がこれらの使役についていたのがわかりました。また、各宿場町には同様な助郷の組織がそれぞれに割り当てられたことを考えると、当時の物流の多くの部分が使役に応じた百姓たちの肩によっていることに思いが至り、本当の縁の下の力持ちと実感せざるをえません。


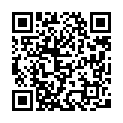
コメントを書こう!