桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
Ⅰはじめに
私は皆さんが今迄、桶川という地域を学び、いわば桶川学とでも言うべきものの構築に向かって精進されているという風に感じております。この会には、ネイティブ桶川の方、既に親子2代、3代の桶川土着民になろうとしている方、他所から来た新参者、いろんな桶川人がいます。この桶川人は日本、世界に繋がり、交流しながら日々の生活を営んでいます。このような人間関係においては、いわゆるお国自慢や郷土の誇りなどの話に当然話題が行くこともあるでしょう。また、日々の生活を営む中で誇りが糧になる場合もあるでしょう。そんな時、今日の話が参考になればと思います。また、観光地としての桶川というようなものも視野にいれた話にしたいと思います。
Ⅱ世界に誇る
ここでは、市内に存在する様々な遺産などのうち、世界1だと考えられる例についてご報告させていただきたいと思います。やや、こじつけもあろうかと存じますが致し方のないことだと思いこんでいます。
1)後谷遺跡出土の櫛
後谷遺跡は、縄文時代草創期、早期、中期、後期、晩期の遺跡ですが、特に後期・晩期の資料は、縄文文化を考える上で重要な多くの情報を提供してくれました。この資料の中に3点のほぼ完形品の縦櫛があります。櫛自体は青森県是川遺跡や新潟県青海(おうみ)遺跡などで出土例があります。しかし、歯先まできちんと残っている例は桶川の後谷遺跡例が唯一の例となっています。
縄文文化は日本固有の文化と考えられ、世界に例のないものです。従いまして世界に誇れる遺産と考えてよかろうと思います。
日本の風土は、年間平均1,500ミリ以上の降雨量がある高温多湿の気候です。また、私達の家が建つ台地は、アカ土と呼ばれる火山灰であるロームに厚く覆われています。桶川では30cm前後地表を掘るとこの層が顔を出します。このローム層は酸性土です。したがって、このような気候と土壌が有機物の遺存を不可能にしています。砂漠地帯や寒冷な気候の地域(ゴビ砂漠やヨーロッパ)で、ミイラや布が残るのとは大きな違いがあります。その点、湿地はそれと同じような条件があります。水分が酸素を遮断し、有機物(木や草、骨など)を腐食から守ってくれます。しかし、発掘中の水の処理には莫大な費用が必要になりますし、水の中から出土した有機物は、空気中に放っておくとすぐ炭化してしまいます。したがって、保存処理をしなくてはなりません。それにも多くの費用が必要となります。


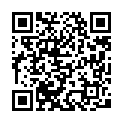
コメントを書こう!