中山道宿場巡り(1)蕨宿探訪記
2011/04/23
地文連中山道宿場巡りの1回目として,昨年(2011)4月23日(土)午前小雨の中桶川駅改札に集合,会長以下13名程が集合した。その後蕨駅西口に 降り立った。主な立寄り先は①城址公園②和楽備神社③三学院④徳丸家跳ね橋 ⑤中山道散策⑥蕨本陣跡⑦蕨市立歴史民俗資料館⑧同分館⑨長泉院梵鐘 下車駅蕨駅が開設されたのは明治28年で,当時中山道蕨宿の町の中心から約1㌔米も東にあった。
『蕨宿』は板橋宿から2里10町,江戸から2番目の宿,本陣2,脇本陣1,旅籠23軒,国道17号線に並行する約1㌔の域内が中山道蕨宿だ。開設は1612年とされ今年で400年となる。旧街道沿いには商店街が続き古い民家もちらほら, 商家も昔の趣をのこしている。直線の路面は緩やかな曲線を描く道となり,街路樹が歴史的風情を醸し出してている。板橋より荒川を『戸田の渡し』で渡る風景は英泉画『木曽街道蕨驛戸田川渡場』にあり,荷物は担ぐものだった昔の旅人,馬も乗り込む乗合船は旅愁を誘う情景となっている。
駅前商店街を中山道へ2/3程進むと『蕨城址公園』があり市民会館がある。蕨城は南北朝時代に渋川氏が館を構えたのに始まり,永禄10年(1567)上総三舟山合戦での渋川氏の戦死に伴い廃されたと云われている。城址は約1町歩(9920平米)程である。江戸時代初めには鷹狩用の休憩地『御殿』として蕨城址が利用された。中央2丁目の『宝樹院』には三舟山合戦で戦死した渋川公と榛名湖に入水した夫人を祀った石碑がある。昭和36年文学博士諸橋徹次撰書で立てられた『蕨城址碑』前にて一同記念撮影をした。城址公園内には『青春』の碑が建っている。蕨市は戦後第一中学校にて全国初の『青年式(発祥の地)』が行われたとして知られている。詩の原作者は,米国サムエル-ウルマンで蕨出身の岡田義夫氏が翻訳したものだ。
隣地には『和楽備神社』がある。境内の池は,その昔の蕨城を囲む濠跡の一部であった。社伝によれば室町時代に蕨を所領とした足利将軍家の一族,渋川氏が蕨城を築城の折,八幡神を祀ったのが最初で,江戸時代には蕨八幡と呼ばれ,明治44年には町内18社を合祀して『和楽備神社』と改称した。神社名については不満の起きないように地名を使うこととしたが,『蕨』では重みがないので当時の春宮侍講に依頼し,万葉仮名を用い現在の神社名となった。因みに命名者は文化文政時代の有名な国学者本居宣長の曾孫に当たる方だそうです。例大祭は毎年10月の中旬に10数基の神輿と山車が練り歩く。数年前には放火により社殿は全焼したが氏子寄進により再建され年末(2011)には百周年記念行事が盛大に挙行された。


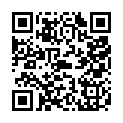
コメントを書こう!