信州の古墳と防空壕 ~第2回地文研県外バス見学会~
2011/05/07
天沼 正明
日時:平成23年6月7日(土)7時~17時30分
交通:小型バス、天候:晴れ、参加員:総員20名

見学地1 松代象山地下壕
この地域にはあの大東亜戦争末期に政府機関などの疎開先として、昭和19年11月から終戦の8月15にまで工事が進められた壕が3か所存在します。当時の設計図の表書きには「松代倉庫新設工事設計圏」と記され、イ号倉庫(象山=現見学可能地)、ロ号倉庫(舞鶴山=天皇行在所、現気象庁精密地震観測室)、ハ号倉庫(皆神山=当時倉庫に使用)の3ケ所で大規模な防空壕でした。9か月間に約2億円の巨費(当時の陸軍隼戦闘機が1機25万円)、延べ300万人の住民、朝鮮人が動員(3交代の突貫工事)され、終戦までに約10km、75%の進捗率と言われています。
今回の巡検では時間の関係から、象山(幕末の松代藩家老佐久間象山の名前の由来)の下に掘られた政府機関が疎開する予定の壕を見学しました。入口はやや狭く、幅約2mで斜傾し50mほどで突き当り、右に直角に曲がるとまた50mほど続き、急に幅4m、高さ2.9mの幅の広い壕となり、 この先は50m置きに左右に同規模の壕が掘られています。全体的には格子状の配置になっており、総延長は約5,900m、概算掘削土量約60,000㎥と推定されています。壕の掘削開始は昭和19年11月11日11時11分に開始したと伝えられています。壕の壁には掘削機のロットの痕跡が生々しく、折れたロットもそのまま残されています。掘削に従事した労働者は朝鮮半島から強制的に連行された人々が多く、組別に競争で工事を行わせ、掘削量の少ない組は食料を減らされようです。また、地元の中学生などが作業を手伝っている写真がNPO法人「もうひとつの歴史館・松代展示室」に展示されていました。
この壕の一部は内装も出来上がっていたようで、皇居では天皇をこの松代までお連れする特別な装甲車のような車3台が作られ、その操縦訓練が開始されていたといいます。戦後、この壕を昭和天皇が見学に来た折、「誰の命令でこんなものを作ったのか」と質問したそうです。どのように答えたのかは聞き漏らしてしまいました。
見学地2 森将軍塚古墳・森将軍塚古墳館 長野県立歴史館(長野県長野市)
上記の3施設は有名な「杏子の里」近くの「科野の里歴史公園」内に所在します。


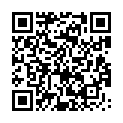
コメントを書こう!