中山道宿場巡り(1)蕨宿探訪記
2011/04/23
中山道本町通りを北行し≪せんべい満寿屋≫の所を右折して『三学院』 (金亀山極楽寺)へ向かう。真言宗智山派,本尊は平安時代後期の慈覚大師作と伝えられる十一面観音を持つ古刹である。境内には鐘楼と三重塔が本尊大伽藍左に凛として建つ。正面の仁王門外に蕨市指定の文化財が開け放たれた御堂の中に静かに並ぶ。『子育地蔵』『地蔵石仏(目疾地蔵)』と『六地蔵石仏』である。目疾地蔵の両眼には味噌を塗って願を懸ける慣わしで,味噌がうず高く塗られ,やや怪異な顔かたちになっている。『子育地蔵尊』は元禄7年(1694)の造立で、火伏,子育,開運の霊仏として近郷近在には勿論,江戸にも良く聞こえて参拝者が絶えなかった。『七番日記』をみると,文化7年(1810)5月,郷里を志した一茶が当山の前に来て右手に地蔵尊を拝したと言う記事がある。墓域には幕末戊申戦役彰義隊にて活躍した蕨出身の『伴門五郎』の奥津城がある。4月下旬から5月上旬には天然記念物の藤が見頃を迎える。
≪跳ね橋≫織物問屋としての徳丸家や氏原家<菱屋>などのある北町3丁目 は屋敷町らしく人通りも少なく閑静である。徳丸家の裏手へ廻ると有名な 『跳ね橋』がある。 幅一間位の溝川が屋敷に沿って掘られて一枚板が架けられている。織物女工屋や雇男の逃亡に備えたものである。蕨及びその付近の浦和,大宮,川口,鳩ヶ谷,与野,上尾,入間,行田などの一帯は埼玉県南織物生産地帯として全国的に知られ,明治大正期には一時殷盛を誇った。筆者が中学時代頃までは蕨の下蕨,塚越地区辺りにも織物工場が音を立て操業していた。 『蕨宿本陣』は慶長11年(1606年)蕨宿開設時,蕨城主渋川公の武将佐渡守 岡田正信の子正吉が本陣,問屋,名主の三役を兼ねたことに始まると言う。本陣2軒,脇本陣1軒,旅籠屋23軒があった。本陣跡に隣接して 『蕨市立歴史民俗資料館』がある。往古の蕨宿内の旅籠の実物大の店頭の様子,食事,本陣大名の食事内容などが復元展示されている。また戦前,戦後昭和期の 民具他などの展示もあった。


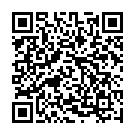
コメントを書こう!