桶川町の繁栄を
2012/03/31
斉藤 勝
桶川の町に住んで四十数年になるが、今でも故郷が懐かしく思い出す。私の出生地は上州名物、空っ風で名を馳せている群馬県高崎である。冬季は、上越国境の山々から吹き下ろす赤城おろしの強風が、寒さが身に染みてくる。桶川の地に住んで空っ風が少なくて、ほっとしている。
昭和2,30年代、高崎線で群馬県から東京へ向かう途中、桶川駅を通過する。桶川は小さな町であるが乗降客数の多い駅であると思った。居住して分かったことは、桶川住民はもとより、近辺の上尾や菖蒲、川島、北本の一部の住民が乗り入れている事である。そのため、高崎鉄道管理局での乗降客数は、常に上位のランクに入っていた。
桶川の町は、高崎の町と通じるところがある。それは両町とも、中仙道沿いに発展してきた町である。高崎は城下町として発展し、中仙道の中で最も繁華な宿場であった。その上、越後へ行く三国街道や富岡方面へ向かう分岐点であり、交通の要地として賑わった。 しかし、宿場としての高崎には本陣も脇本陣もなく、旅籠も少なかった。それに町は早くから開発され、今ではかつて宿場の面影は薄れてきた。
その点桶川の街道筋は、土蔵造りの家や旅籠、桶川宿本陣遺構など、江戸時代の宿場の面影を残している。当時の桶川は毎月五と十の日に市が開かれ、麦などの産物の取引が盛んに行われた。その名残の穀物問屋であった土蔵造りの家が、今でも何軒かある。また、この地域は紅花の産地であり、栽培が盛んに行われた。武州の紅花は品質が良く、京都の紅問屋で珍重された。中仙道沿い近くの稲荷神社には、紅花商人が寄進した医師灯篭二基あり、商人の名が刻まれている。その側に大きな力石が置かれてある。


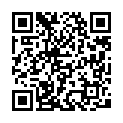
コメントを書こう!