伝統芸能文化の振興シンポジウム ~繋げたい!桶川の伝統芸能~
川田谷の三田原ささら獅子舞保存会の大野隆三さんは、ささら獅子舞と万作踊りについて話してくださった。領家の獅子舞とは形態が少し異なるようだ。
かつて、獅子舞は長男だけが継承し、次男三男にはさせないという厳しい制度があった。子どもの頃から男の子には竹笛をやらせていたが、昭和47年頃までは長男以外は参加できなかったが、その後は誰でも参加して行われている。
女獅子は小学生の6年生位から、4人一組でする。3~4年やって中獅子になり、中獅子は2~3年やって大獅子になる。ここで頭抜けといって卒業になり、天狗役で隠居になり指導役となるのが慣例。いずれにせよ、4キロもある獅子頭を付けて1時間40分もの踊りとなるのだから、大変なことである。準備・練習・奉納は地域の協力なくしては出来ないことで、村全体の行事として行われている。
昭和35年まで青年会を組織して継承してきたが、以後13年間途絶えてしまった。領家と同じような事情により、時代と共に子どもも大人も地域にとどまらず外へと出る機会が多くなり、継承できる人員が減ってしまったことが大きな原因だった。
万作踊りは昔の青年団や、その後青年会などが引き継いできた。36年から11年ほど途絶えていたが、現在では復活して男踊りも含めて30数人が加わっている。


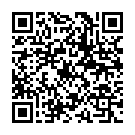
コメントを書こう!