川田谷と長命寺についての思い出
その後、時も過ぎ、お互いに逢う機会もなくなり、1年1回の年賀状のやり取り位になり、長命寺の事も、そのままになってしまった。昨年、この友人からの年賀状に長命寺の事が久しぶりに書かれてあり、昔の色々な事を思い出し、当時の写真や資料などを捜したが見つからず、たった1枚、当時長命寺の留守居をしていた人から頂いた名刺を捜し出すことが出来た。その名刺には「建設省関東地方建設局東京技術事務所機械課建設技官 内田 一、住所は東京都墨田区立花町1丁目・・番・・号、電話(・・・)・・・・番」と書かれ、裏面には、自分が書いた龍慶山長命寺、岩槻小溝にて、昭和42年12月17日、八木崎より歩いた道順や、電車代、慈恩寺へ寄った事、そこから岩槻駅までのバス代等が書かれてあった。
この名刺を見て、当時のことが色々と頭の中に蘇り、なつかしさでいっぱいになり、そして新編武蔵風土記稿から、小溝村の事や長命寺の事を調べてみた。新紀によれば「小溝村はわずか50戸ばかりの小さな村で,長命寺はその昔は真言宗の庵室であったが元和4年3月改宗して一寺となり龍慶山慈眼院長命寺と号して天台宗慈恩寺の末寺になった」ことが記されてあった。
そんな折、昨年の6月24日春日部まで行く用事が出来、この機会に再度長命寺を訪ねてみたい気持ちに駆られ、春日部での用事を済まし、帰り道、再度、八木崎駅で下車し長命寺をめざし歩き始めたが、時代の変化で、あたりはすっかり開発され、何度か聞きながらやっとの思いで長命寺にたどり着くことが出来た。
早速、庫裡へ行き、声をかけたが留守らしく返事がなかった。庭から本堂を眺め、昔の思いが甦り、墓地の方へ行き歴代住職の墓を見て川田谷出身の住職の墓石を見つけ出した。その卵塔の全面には「佛乗院権小都亮瑞和尚位、裏面には昭和19年5月5日寂、そして台石には埼玉県北足立郡川田谷村内田國三郎三男として、明治8年10月8日産、同村泉福寺住職根本亮継師に従い、明治17年11月得度、明治29年9月長命寺住職、長福寺、持宝寺兼住、行年70才にて寂す。昭和29年5月9日建設、遺弟第12世内田大三」と記されてあった。そして本堂の庭に戻り境内の片隅に建立されてある本堂修繕記念碑があった前面に「龍慶山本堂修繕記念碑浅草寺大僧正榮海謹書、裏面には奉納された人々の氏名と金額、住所、役員名等が記され、大正14年12月下院、当山現董亮瑞代、知友入間瀧岩院主亮貫書」と建立された年月日等が記されてあった。


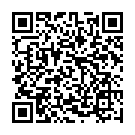
コメントを書こう!