第3回地文研県外バス見学会「帝都の戦争遺跡の巡検」(報告)
今井 正文
第1回は山梨の縄文文化、古墳文化、浅間信仰、第2回は、信州の古墳文化、終戦末期の国家的防空壕施設の巡検を実施した。今年度は、東京、神奈川で、現代史の遺跡を主とした。平成24年6月10日に実施し、小型バス1台で、天候は晴れ、当日の参加人員25人であった。以下、訪問した施設毎に概要を記し報告としたい。
調布飛行場(掩体壕)
 この飛行場は、昭和16年4月に公共飛行場として開港したが、昭和17年以降は陸軍の第244戦隊他の基地として使用された。大東亜戦争当時の配備機は3式戦「飛燕」で、昭和20年前後には、成増飛行場などと共に帝都防空の任務にあたった。震天制空隊はB29に空対空の特別攻撃をおこなった。それらの使用機を空襲から守るために作られたのが掩体壕で、現在公園として整備された中に、2基が文化財として保存された。
この飛行場は、昭和16年4月に公共飛行場として開港したが、昭和17年以降は陸軍の第244戦隊他の基地として使用された。大東亜戦争当時の配備機は3式戦「飛燕」で、昭和20年前後には、成増飛行場などと共に帝都防空の任務にあたった。震天制空隊はB29に空対空の特別攻撃をおこなった。それらの使用機を空襲から守るために作られたのが掩体壕で、現在公園として整備された中に、2基が文化財として保存された。
第九陸軍技術研究所(登戸研究所)
 この施設は、陸軍が使用した様々な兵器の研究、開発をおこなった施設で、登戸研究所と通称された。ライター型写真機、偽札、細菌兵器、風船爆弾なども開発した。この敷地は、明治大学が使用しており、当時の施設の一部が残され、「明治大学平和教育登戸研究所資料館」として、解放されている。
この施設は、陸軍が使用した様々な兵器の研究、開発をおこなった施設で、登戸研究所と通称された。ライター型写真機、偽札、細菌兵器、風船爆弾なども開発した。この敷地は、明治大学が使用しており、当時の施設の一部が残され、「明治大学平和教育登戸研究所資料館」として、解放されている。


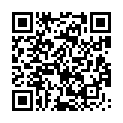
コメントを書こう!