中山道ぶらり歩き旅Ⅵ ~深谷宿から本庄宿~
伝説の古刹を、たどりながら、群馬県境までを目指す。
中山道、深谷宿から本庄宿まで2里25町(11km)の道中“ぶらり歩き旅”を続けます。
深谷宿、北はずれ萱場稲荷神社周辺を通過すると道は右に蛇行、宿根で、新道と合流するが突き抜け、新道と平行しながら岡部南で再び合流し岡部町へ入ります。岡部町は阿部氏(江戸初期岡部の領主)ゆかりの源勝院や、岡部六弥太(鎌倉武士)が眠る普済寺など、由緒ある古刹が数多く、集まる地域です。
早速、北へと、歩を進めると、岡部北の信号際の右に「源勝院」、左に「岡部陣屋跡」があるとのことですので、まず、右側の「源勝院」へ見聞に行ってみます。入りますと.境内は、見事に整理、清掃された綺麗で“こじんまり”とした立派な寺院でした。ここが、天正18年(1590)に岡部の領主になったという安部氏の菩提寺で、参拝すませます。
再び、中山道へもどり、左側50m程入った所に「岡部陣屋跡」があるというので見聞に行く。四方15mほどの石囲いがあり、現在は歴史を記す石碑が建ち、陣屋跡の説明内容を読んで見ると弘化3年(1846)に高島秋帆(西洋軍事学を修得し高島流砲術を創出した人)が幽閉されていた場所で、その後、高島秋帆は、江戸屋敷に移された。陣屋跡を確認して再び中山道へ戻り、北へ歩く2つ目の信号に普済寺とある。その手前.普済寺の案内、進行方向右折となっている。「普済寺」へ見聞によると「栄朝禅師」を開山とした禅宗の名刹という別名「玉竜山」。寺の入口には「岡部六弥太忠澄旧跡」の石柱が建ち、六弥太が臨済宗の僧、栄朝禅師を開山として建立したと伝えられる。栄朝は栄西に師事し、関東地方に禅宗を広く布教しようと活躍した。しかし、寺はその後曹洞宗となった。岡部六弥太は鎌倉武士で、寺の裏手に県の指定遺跡である六弥太墓と伝える五輪塔群がある。(六弥太の墓石の粉を呑むと女子には子が出来、乳が出るようになるという。)


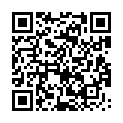
コメントを書こう!