桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
2)稲荷神社の力石
中山道は江戸時代に幕府によって整備されたいわば官道です。この街道の整備に伴い設置された駅が桶川宿です。この桶川宿の鎮守が寿2丁目に鎮座する稲荷神社です。この稲荷神社にはさまざまな遺産がありますが、この神社の境内に、「大磐石」とかかれた力石があります。地域文化研究会の皆様の努力と桶川市の協力によって2006年に体重測定が行なわれました。610kgで誤差は+-500gとの報告がされており、力石の研究者である高島先生の話によれば、今のところ日本で1番重たい(大きい)力石ということです。力石はご存知のとおり力比べに使用された石で、その多くは一定の様式を有しています。
力比べと言う行為は世界にいろんな形態で存在しているようですが、石を用い、神社に奉納されるという形式の力比べはやはり日本固有の文化と言ってよかろうと思います。神社が日本固有のものですから当然といえば当然ですが。日本固有の文化であり、日本で1番大きい力石は、当然世界で1番大きい力石ということになるのではないでしょうか。蛇足ですが、この力石の文化は西低東高のようです。(文化は西からのアンチ)
3)三角形の本丸跡 (三ツ木城)
桶川市に7箇所の城跡が知られています。日本国内の城は、古代、中世、近世に分類され、皆さんが良くご存知の城の殆どは中世に起源をもちながらも近世の城で、石垣、水掘りなどの構造物や天守閣、櫓などの建築物に象徴されます。それに引き換え古代・中世の城は、建築物に乏しく石垣や土塁認識されません。あるいは、発掘調査により埋まった堀が、溝として発見されます。近世の城の多くは、中世の城を改築、増築した例もあります。また、福岡県の大野城は古代を代表する城で、町ごと囲む朝鮮半島の城を模範に築造されました。神籠石と呼ばれる石垣も古代の城といわれています。埼玉県の嵐山町の菅谷館は中世を代表する城と言えます。
荒川の左岸に流れ込む石川がその中流域に作った湿地を東北の眼下に臨む台地に三ツ木城跡の本丸が所在します。県選定重要遺跡となっているこの城には、一部に二重の土塁が残り、土塁の頂上と掘りの底の比較差は3mほどあり、側に立つとちょっとビックリします。この土塁の平面形態は3角形になっており、国内では他に類例が知られていません。その意味では日本でこの桶川だけにあることから世界に誇れる遺産ではないかと思います。
なお、円形の城は藤枝市の田中城があります。この円形の平面形態も城にはめずらしいものだと思います。ここの城主は桶川を開闢したとされる西尾沖上(にしおおきのかみ)と同じ称号を持つ人物が勤めています。(同一人物かどうか不詳ですが) 藤枝の田中城のと桶川の三ツ木城は、三角形と円形の縄張り、中山道と東海道の宿場町、西尾沖ノ上言った関係者、何かの縁なのかも知れませんね。それとも5街道の宿町の縁でしょうか。


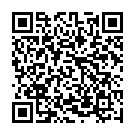
コメントを書こう!