桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
4)五丁台の板石塔婆(青石塔婆、青石板碑)
五丁台は桶川市の最東部に位置し、この地域に接してほぼ南北に流れる元荒川が菖蒲町との境になっています。この元荒川は、市の西端を流れる荒川に瀬替が行なわれ、江戸時代以前までこの地域と秩父方面、東京湾方面を結ぶ重要な河川であったと考えられます。
元荒川の右岸に長野家の一家墓があります。この墓に高さ3m10cmの青石塔婆があります。この塔婆は青石板碑とも呼ばれ、埼玉県の秩父地方や小川町方面 で採取される緑泥片岩という石を用いた埼玉県を代表する供養塔です。この石は緑色で、薄く剥がれやすい性質を有する石で、板碑の形態を規定していますの で、武蔵型板碑とも呼ばれます。板碑という供養塔はほぼ日本全国に見られますが、五輪塔と共に中世を代表する供養塔です。しかし、五輪塔や宝篋印塔(ほう きょういんとう)のように近世につながりませんでした。また、生まれた過程も良くわかっていません。
3mを越す板碑をいわゆる大型板碑と呼んで おり、小池先生の研究によれば11例が確認されているようです。この11例の内、最古の例がこの桶川の板碑です。大きさや、古さを基準にすれば、皆野町や 江南町の例がそれぞれトップですが、両方を同時に満足させる例は、この桶川の例となります。日本独自の供養形式であるこの板碑は当然世界で、1番大きくて 古い板碑だといっていいと思います。ちょっとこじつけ過ぎでしょうか。?お後がよろしいようで、話のスケールをちょっと下げましょう。


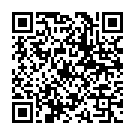
コメントを書こう!