桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
2)川田谷飛行学校
この飛行学校は、桶川市川田谷若宮に所在し、荒川を西側の眼下に望む高台に位置します。昭和12年に長野県上田飛行場、所沢飛行場、栃木県金丸飛行場と共に熊谷飛行学校の分校として会場し、昭和20年までに1,500~2,000人航空兵を養成したと推定されます。戦前の日本国内には陸海あわせて約160箇所の飛行場があったようです。終戦間際に作られた秘匿飛行場を加えると240ヶ所程度の数になる様です。これらの飛行場は、大きく教育隊と実戦部隊配備の飛行場に分かれますが、中には太刀洗飛行場のように同居していた飛行場もあります。このような飛行場施設は学校、実戦部隊に関わらず、多くの兵員が寝泊りしたり、飛行機を格納する多くの施設を有していました。しかし、当時の航空隊施設は、鉄筋のものは少なく、多くが木造施設でした。明治時代に各地に設置された連隊本部や海軍兵学校の江田島の建物に比較すると、とても安普請といえるでしょう。また、戦後このような飛行場施設の多くは無用の長物(広物のほうが適切ですが)となり、畑や住宅、工場、公園などに生まれかわりました。
桶川の飛行学校の校舎は全てが残っているわけではありません。飛行場にあった格納庫やその付属施設、本部棟、事務等、教室棟、食堂・風呂場棟などは既に解体されてありません。後者の4施設は昭和50年代まで残っていました。それは、校舎全体が、引き上げ者や焼き出された人達の住居にあてられたからだといえます。平成21年に最後の居住者が退去し無人になりました。土地と建物は旧軍が買収したものなので、財務省の所有で、建物のみ桶川市が財務省から借り受け管理しており、国に借地料を支払っていました。住民が居なくなり、いわばこの桶川市営住宅廃止に伴い、更地にする必要がありました。残されている守衛室、宿泊棟(下士官室。医務室を含む)、便所、車庫、弾薬貯蔵庫?(コンクリート製)、防火水槽2か所などが、消滅するのは歴史資料の喪失でもあるので、桶川飛行学校語り継ぐ会が中心となり地域文化研究会なども協力して署名活動を展開し、平成21年に市が国から土地を買い受けました。
これらの建物が乗る台地のすぐ東には「谷津田」(ヤツダ、ヤチダ)とよばれる谷水田が良好な形で維持されています。多くの谷が埋め立てられていく中で、このような天水や井戸水を水源とする谷水田は、かつての景観を偲ぶ遺構ではないかと思います。
この飛行学校の建物と谷津田を一体的に活用した施設が出来たなら、これも他にないものであり、多くの見学者を呼べる可能性があると思います。建物は木造であり甚だ貴重品の保管には不向きですが、谷水田の体験型宿泊施設には使えます。また、防火建物には、当時の遺品や飛行機を展示してもいいでしょう。また、敷地内にはオオムラサキの食草であるエノキの巨木あります。飛ぶと言ったキーワードで、自然と平和をテーマにした記念館ができるといいなと思っています。どのように活用するかは別としても、いずれにせよ、後世に残すべき財産と思います。


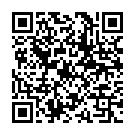
コメントを書こう!