桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
3)桶川宿の都市計画
桶川宿は、皆さんもご存知のように江戸時代に整備された五街道の一つである中山道の宿場町です。当時は桶川駅といっていたようです。駅は馬が集まるという意味で、当時の物流の原動力が馬であることを考えるとうなずけると思います。明治初期の東京の地図を見ますと東京駅は東京スーションと記入されています。この当時、宿場町時代の駅のイメージと汽車の駅(停車場)のイメージが合致しなかったのでしょう。あるいは新たなステーションの訳語が開発されなかったのかもしれませんね。
中山道はその大部分が古代の駅制の東山道のルート同じであるといわれています。中世にも道として利用されたと思われますが、江戸から倉賀野間は中山道の整備に際して新たに宿(駅)として指定されたのだと思われます。したがって、当時における最新式の駅と言えるのだと思います。江戸から数えて6番目のこの桶川宿は、当時の代表的な遺構である本陣の一部が所有者・関係者の努力によって伝えられています。本陣遺構は県内に2例(桶川と深谷)ありますが、桶川のものは県指定文化財にも指定されています。また、浄念寺の門や商家など江戸から明治にかけての遺構も比較的多くあります。蕨市の博物館の学芸員は、お客さんに「どこに行けば宿場らしい雰囲気が味わえますか」と問われると「桶川に行きなさい」と答えるそうです。県内の宿場町は9宿ありますが、その中でも東京に近くて風情を良くのこしていると思われます。桶川宿の中山道の広さは江戸時代から変っていません。あの広さのようでした。それと、路地を含め西側は夜盗道も良く残っています。この夜盗道と本通り(中山道)を結ぶ路地がよく残っています。「浄念寺」、「大雲寺」はそれぞれ「下の寺」「上の寺」と言われていますが、この寺は本陣を起点に考えるとほぼ等距離に位置します。また、本陣や問屋場が位置したところが中心部ですが、この部分の奥行きがもっとも深く、夜盗道まで距離がありますが、宿外れに行くに従い、夜盗道までの距離は短くなり、したがって奥行きが減少します。これらの遺構は、明確な設計のもとに作られた証拠だと思います。この地割が桶川にはまだよく残されています。したがって、宿内の道路は江戸時代に造られたものといえます。駅と中山道を結ぶ道路は、市内で最も短い県道です。(約250m)この道は桶川駅を作る時につくられた道で、明治時代の道路です。内藤スタンドにはこの道路用地を寄附したときの書類が伝えられています。中山道から国道17号までの道は戦後に作られた道で昭和の道です。また、駅周辺の南2丁目の道などは、戦前に内務省によって買収が進められ、拡幅されています。
このような道路を時代によって塗り分けたら、みんなが人目で各時代を認識することが出来、しかも、次第に現代に近づいてくる様子を重層的に認識、実感できることでしょう。また、電線類も裏通り(夜盗道)に回し、路地から導入すれば中山道の電柱を無くすことも可能でしょう。でも私は、かつての木の電柱を復活させたほうが、例がなく面白いと思っています。また、中山道に面した家には、家の履歴書を設置したいと思います。履歴書は、屋号や昔の写真や現状の建物の建築年代や特徴などを書いたものをイメージしています。町のはしから端まで見て歩くと江戸時代から現代までの建築史が実物を比較しながら体感できると思います。いずれにせよ、宿場時代の伝統に配慮したちょっとした工夫で、多くのおお客さんが訪れ、自分達も住んでいて気持ちの良い町ができるのではないか。こんな町ができれば、少なくとも埼玉県下くらいには誇れると思うのですが。


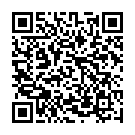
コメントを書こう!