桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
Ⅳあれば誇れるカナ?
ここでは、こんなものがあれば、あるいは素材をこんな風に工夫、加工したらいろんな人が、この桶川に来てくれるかなといったような、いわば観光も視点におきたいと思います。観光といっても大型バスを何台も連ねるのではなく、数人がグループで複数回訪れたくなるような、そんな観光です。そして、できるだけ市民が参加して作れるものをという観点で話したいと思います。
1)井戸水で育つ米 井戸水米
大宮台地は水の乏しい台地です。しかし、台地の縁にはかつてたくさんの湧水があり、井戸を発見するまでの原始・古代人に格好の住処を提供していました。稲作が伝わってきた時も、樹枝状に発達した小さな谷の湿地は、この湧水とあいまって、稲作に必要な水田を提供しました。しかし、その後、(5世紀)稲作はより広大な沖積地にその主な舞台が移行していき、大宮台地は、水田稲作の後進的な地域になってきました。特に江川流域では、耕地整理が実施される昭和30年代まで、ツミタと呼ばれる稲作が行われていました。この稲作は田植えをせず、籾をばら撒くもので、収穫もソリや田船を用いておこなっていました。このように、水田を耕すこともままならず、畜力(牛や馬)も活用できない、もっぱら人力がたよりのこの水田は、広大な沖積平野に作られた乾田に比較すると、その収穫量は半分程度です。一般的に乾田では単当たり8~10表前後が標準といわれます。
桶川の川田谷、日出谷、坂田、加納地域ではこのように水田経営は、収入の一部としかいえない状況です。それを物語るはなしとして、かつては麦8~6、米2~4が当たり前の主食だったと言われます。このような地域において、戦後導入された農電と呼ばれる200ボルトの電力は、井戸の掘削技術の向上とポンプの普及から、台地の畑を水田化することが始まりました。これを陸田と呼んでいます)昭和40年代からの出来事になります。全国的には減反が進められていましたが、この桶川地域では、水田面積の拡大が行なわれました。米のご飯の願が多くの畑や山林を水田に変えたのではないでしょうか。(多くの場合、陸田になる前の畑では桑が栽培されていたようです)
多くの水田は、山に降った雪や雨が少しづつ流れ出し、水田の水になります。いわゆる表面水です。現代社会においてはこのような水は、水田に到達する前に工場や車の排気ガスや洗剤などの化学物質を含む生活汚水の流入が予想されます。
しかし、当然、山間部のような貯水施設(山)がない桶川地域の陸田は、井戸水が使用されています。殆ど汚染の心配のない水です。このような素晴らしい水でつくられたお米は、日本に誇れる米ではないかと思っています。安全な食が叫ばれている今日、このような米の存在を、生産者が自覚し、多くの消費者に知ってもらうことが先決だと思います。食にかんする桶川の財産と思うのですが。「井戸水米」なんとか商品化したいものです。


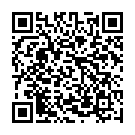
コメントを書こう!