桶川壱番物語 ~桶川の遺産~
2012/01/14
2)白タンポポの土堤
桶川には西洋タンポポ、関東タンポポ、シロハナタンポポの3種があります。もっとも多いのが西洋タンポポです。都市化の進んだ場所に多いといわれます。関東タンポポは少し自然の残ったところにあり、城山公園を流れ出る石川の土手には多く確認されています。シロハナタンポポは数箇所で確認されており、その数はもっとも少ないものです。このタンポポは関西や九州では多く見られるようですが、関東では結構少ないようです。
このシロハナタンポポで覆われた土手を作ることが出来たらきっと面白い空間が出来るのでないかと思います。
地元にあるシロハナタンポポを各自が増やし、その苗を土手に植える。市民参加で充分こんな素敵な土手がつくれるのではないでしょうか。
3)アゲハ蝶の飛交う駅
桶川駅は首都東京から約40km圏に位置する近郊の駅です。首都圏近郊の駅は、近年の都市化によって旧来の景観は急速に無くなり、地域性の乏しい新駅に変っています。そのような変化のなかで、この桶川駅が個性的な駅にならないか。出来れば安価で、伝統にも留意したものは何かないか。そんな、ことを思っている時に出会ったのがジャコウハゲハでした。
この蝶は馬の鈴草のみを食草とし、雌雄で体色が異なる大型のハゲハ蝶です。この蝶は非常に優雅にヒラヒラと飛び、人の近くにも平気で近寄ります。アオスジアゲハやナミアゲハとはこの点で大きく異なります。一説によれば、食草の馬の鈴草が毒草であるため、この毒が体内に蓄積されるので、鳥などの餌になる危険がないから優雅な飛翔ができるとの説明もあります。また、馬の鈴草の名称は街道を行き来する馬の首につけた鈴に、その花が似ていることから名づけられたと言われています。また、蛹は「番町皿屋敷」「播州皿屋敷」の主人公とも言うべきお菊さんがモデルと言われます。この蝶の蛹は井戸につるされたお菊さん姿と重ねたもので、「お菊虫」とも呼ばれています。江戸時代の人がつけたもののようです。明治以降の学者さんと違い、命名が粋ですよね。
宿場町と言えば本陣、問屋、本陣、問屋といえば馬、まさに桶川にふさわしいチョウチョと思います。こんなチョウチョが駅前を優雅に飛交う光景を想像してみてください。(蝶がキライナ人はごめんなさい)しかも、東京から40km圏です。そんな駅はほかにあるでしょうか。桶川にくればジャコウアゲハが見られる。そんな駅があってもいいのではないでしょうか。
オスのジャコウアゲハはかぐわしいにおいがするそうです。昔の女性の化粧品のような?。(私自信、本物のジャコウの匂いが解かっていません)メスはフルーティな香りがするそうです。一寸眉唾ですが。
なお、昼は蝶々ですが、夜はフクロウの類が飛翔すれば、昼夜を問わない空の生き物が飛交う桶川駅が現出しそうです。住んでいただけるかどうか解かりませんが、少なくとも、フクロウさんの誘致運動をしても良いかも知れません。


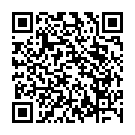
コメントを書こう!