栃餅作り
2012/03/31
 当時、檜枝岐では栃餅をまだ作っていた、キチばっちゃんも作っていた。宮前食堂を経営していて、食堂の前には秋になるといつもむしろに広げて栃の実を干していた。「いくら干しても干しすぎることはないんだ」と言ってた。
当時、檜枝岐では栃餅をまだ作っていた、キチばっちゃんも作っていた。宮前食堂を経営していて、食堂の前には秋になるといつもむしろに広げて栃の実を干していた。「いくら干しても干しすぎることはないんだ」と言ってた。
~古代食文化を知る~と名打って地文研では、全国の山村から消え去ろうとしている栃餅を作ろうという話が出たのが、平成22年度のことで9月にやっとの思いで檜枝岐から20㎏ほど拾ってきた、文献頼りに数人で挑戦してみたが甘かった全員失敗。
さて、23年度は、まず檜枝岐へ栃の実収集に、そして製法調査に行き、栃餅作りを続けている最後の伝承者・星くに子さんに作り方を教えていただいた。さらに秩父の両神山荘のご主人からも教えていただいた。栃の実収集の過程で桶川にも栃の実が生っていることが解り、檜枝岐の実と比べてみることになった。桶川のものは色が黒く少し小振り。
檜枝岐および秩父、この2つの地方の作り方を表にしてメンバーで作り方を協議して栃餅を作った。一番のネックは「栃の実からアクをいかにして抜くか」これが成功と失敗の鍵を握る。アクを抜いた栃の実を餅米と一緒に蒸かして臼でつきあげれば、おいしい栃餅の出来上がりである。
餅つきは12月30日に江森次郎さん宅で実施。さて、栃餅作りに参加した、杉井・天沼・三好・堀口の面々。我こそはうまくアク抜きに成功し、餅つきの後、酒を飲みながら自慢話に花を咲かせようと、一人ひとり少しずつ独自の工夫を凝らしてアク抜きをした。結果はアクが抜けていたり抜けてなかったり、全員どうもハッキリしない、まずい餅を作る羽目になった。
檜枝岐のくに子さんが「そう簡単にはできないさ、私だって何度も失敗してやっと作れるようになったんだから」・・・・・その通りになりました、24年度改めて挑戦することにしたが来年は成功しなければ。


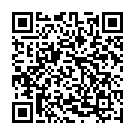
コメントを書こう!