桶川小学校の二宮金次郎像をみて
当時、町の繁栄と共存していた建築職業界の面々が、その恩返しにと、業界の誇りを持って、他校の像とは格差ある、この石像を気張って寄付したのではないかと推測した。
小川会長の話によると、当時の建築職業界の付き合いは、横一線のモノだった。材木商、大工、左官、石工、建具師、表具師、屋根や、畳や等の各職業に差別はなく、仕事上も仲間の付き合いでも同等であった。それが請負制度に推移していくと、同等の付き合い関係が崩れ、上下関係の付き合いへと変わっていった。その上下関係にも派閥があり、縦割の系列が更に複数化したそうだ。
昔は仲間でモノを公共施設等に寄付する場合には、材料商人は所要材料を無料で提供し、職人はそれを用い各自の技能を使い、無償で仕事を仕上げるのが常態で、いわゆる美風があったそうだ。
今では労働組合まで出来、組織は確りしているが、上下関係のある業界では横の連絡が疎かになり、いわゆる“絆”が細く寂しいものがある、と建具師の小川会長は語った。
金次郎サンの石像を見たお蔭で、此の様な建築職業界の時代による組織、仲間付合いの変遷の流れも知ることが出来た。
また後日、本会々員の秋山有世氏により、ご父君・比呂氏の日記に、この像の寄贈から除幕に於ける経緯が明らかになる資料(別記参照)が提供されたので併せて報告する。
備考・桶川小学校の二宮金次郎像は「愛知系石像」である。袴の内に上着を入れ、左足が前に出ている事が特徴である。因みに、右足が前で、上着が袴の外に出ている像は「富山系銅像」、と分けられている。*参考・Goo Wikipedia


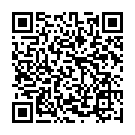
コメントを書こう!