中山道ぶらり歩き旅Ⅵ ~深谷宿から本庄宿~
 「中山道まめ知識」より本庄を紹介
「中山道まめ知識」より本庄を紹介
“幾多の軍の攻撃を受けて数奇な運命をたどった本庄城”本庄実忠が築いた本庄城は、永禄10年(1567)に小田原北条氏の攻略にあい、天正18年(1590)には豊臣の攻撃を受け落城した。その後、徳川方の小笠原氏が入城したが、二代目信之の代で廃城に。数奇な運命をたどった城だという。
“関東有数の規模を誇り繊維産業で栄えた本庄宿”
慶長17年(1612)の本庄城廃城に、前後して中山道の宿場が制定され、城下町は新たに宿駅、本庄宿として発展していく。また、明治以降は全国有数のマユの集散地となり、養蚕の町本庄としてさらなる発展をとげたのである。
“洋風建築が美しいレトロな歴史民俗資料館”
 もとは明治16年(1883)に建てられた旧本庄警察署だった市立歴史民俗資料館。県の文化財に指定されている瓦葺きの二階建てで、外壁には漆喰塗り、ベランダの柱には精巧なコリント式の彫刻がほどこされた瀟酒な洋風建築だ。
もとは明治16年(1883)に建てられた旧本庄警察署だった市立歴史民俗資料館。県の文化財に指定されている瓦葺きの二階建てで、外壁には漆喰塗り、ベランダの柱には精巧なコリント式の彫刻がほどこされた瀟酒な洋風建築だ。
いよいよ本庄宿に入るに当り“本庄宿”について少々記述して見ます。
江戸日本橋から、21里30町40間(87km)、家数1,212軒、人口4,554人、本陣南北各1・2軒、脇本陣2軒、問屋場6ヶ所、旅籠屋70軒(大23軒、中24軒、小23)宿内町並み17町(1.8km)、本陣差し合いの際、代用本陣又は休泊請けに当たる寺院は、安養院・開善寺・威徳院・慈恩寺・円心寺、江戸時代天領・代官・大熊善太郎、支配地高2,158石。宿場内は、四町一宿となっている。


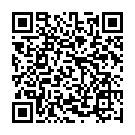
コメントを書こう!