中山道ぶらり歩き旅Ⅵ ~深谷宿から本庄宿~
中山道67宿の中でも、本庄宿は、最大規模の宿場町であったようです。
「本庄宿」内をぶらり歩き江戸から本庄宿への入口、17号バイパスを横切り、直進する(北西に向かう)なだらかな登り坂が500mほど続く、左手に庚申塔が見える。ここを御堂坂(みどうさか)と呼ぶ。坂を越えると、平地になるがそのまま直進すると本庄東中学校前の信号、この辺緩やかに東へ蛇行するが直進する。直ぐ東台4丁目の信号。さらに北へ進むと中山道交差点にどうもこの付近にあった木戸が見付だったようである。
しかし、道幅などは他宿とおなじようで、これが江戸期から続く中山道の面影かな?それ以外、昔の面影を残す物は見あたらない感じ。右手に、本庄氏の居城「城山」当時、付近は城下町で本庄の地名が残っている。城址・八坂神社・城山稲荷があるというので見聞に寄って見る。元小山川が東の下を流れ、まさに自然の要塞か。
城内には神社・稲荷を配置されていたようで、特に城山稲荷は、城跡の一番奥の元小山川際で、そこに大木がある。城山稲荷にそびえる大ケヤキは高さ63m、弘治2年(1556)の本庄城築城の際に献木されたものと伝えられ、県の天然記念物に指定されているとの事。さすがに、ここでは、往時の名残りを感じることが出来る。
この地の北側は、駅前通りになっていて、本庄市役所と警察署が建ち並んでいる。再び、本道に戻り直進すると、本庄駅前通りに出るが通過する。中山道は北西の方向になる。少し歩くと、直ぐ、中央1丁目交差点の右側に、歴史民俗資料館(本陣門・旧本庄警察署建物)があるので入館して観る。
門は北本陣田村家の移築、建物は、明治16年建築(130年前)の警察署を活用している“歴史を感じる資料館“である。ここに江戸・明治の面影を見ることが出来たところで、資料館より南側にある開善寺(曹洞宗)を覗くことに。天正19年(1591)本庄城主小笠原氏が建立。信嶺夫婦の墓があるので、参拝する。宿場内に非常に寺院が多いことに気付く。円心寺・大正院・城立寺・開善寺・安養院・泉林寺・西広寺・佛母寺等。本庄氏の戦国時代からの、城下だったからでしようかね。


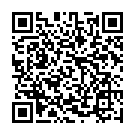
コメントを書こう!