中山道ぶらり歩き旅Ⅵ ~深谷宿から本庄宿~
 本庄宿は元小山川の流れと平行している。川の蛇行と中山道の蛇行が、同じようになっていることを感じながら、本道へ戻り北西へと歩く。高崎線を左に観ながら、北へ暫く行くと行き止まりとなる。千代田3丁目交差点左、下仁田、追分街道と呼ばれ中山道の南を通る脇往還で藤岡・吉井・富岡・下仁田方面へ行く街道です。中山道は右折し100m先を左折して進みます。突き当たりの右に本庄の“総鎮守金鑚神社”が鎮座し、宿場はここまで。宿場の総鎮守ということなので見聞します。
本庄宿は元小山川の流れと平行している。川の蛇行と中山道の蛇行が、同じようになっていることを感じながら、本道へ戻り北西へと歩く。高崎線を左に観ながら、北へ暫く行くと行き止まりとなる。千代田3丁目交差点左、下仁田、追分街道と呼ばれ中山道の南を通る脇往還で藤岡・吉井・富岡・下仁田方面へ行く街道です。中山道は右折し100m先を左折して進みます。突き当たりの右に本庄の“総鎮守金鑚神社”が鎮座し、宿場はここまで。宿場の総鎮守ということなので見聞します。
“金鑚神社”の創建は、欽明天皇2年(541)とありますが、確かなことは不明とのこと。弘治元年(1555)本庄実忠が社殿を改築し総鎮守としている。現在の社殿は享保9年(1724)の建立で、拝殿は安永3年(1850)幣殿は嘉永3年(1850)の建立とのことです。境内には宿西・新田町の市神様も祀られ、正面総欅造りの門は元別当寺白蓮寺の総門で市の文化財に指定されている。クスやモミなどの巨木が生い茂る境内には、18~19世紀にわたって造営されたという、彫刻を施した丹塗りの見事な社殿である。県北最大の宿場町本庄宿は終了ですが、国境まで歩きます。
 金鑚神社を出ると中山道は直角に曲がり(桝形道)、100m程進むと左折する。元小山川と平行している道となる。この辺、本庄市小島という。周辺は、特別の史跡もない暫くすると、本庄市万年寺の信号があり、この先は、児玉郡上里町神保原町という地域になります。右側に橋の石碑「泪橋跡碑」があり、庚申塔が建つ。現在、川はないが石碑には、かつてこの地区の人々が、伝馬役(助郷)に苦しみ涙を流した由来が記されている。江戸時代最大規模といわれた伝馬騒動(百姓一揆)の発祥地だったのです。明和元年(1764)ですから、今から249年前のことです。
金鑚神社を出ると中山道は直角に曲がり(桝形道)、100m程進むと左折する。元小山川と平行している道となる。この辺、本庄市小島という。周辺は、特別の史跡もない暫くすると、本庄市万年寺の信号があり、この先は、児玉郡上里町神保原町という地域になります。右側に橋の石碑「泪橋跡碑」があり、庚申塔が建つ。現在、川はないが石碑には、かつてこの地区の人々が、伝馬役(助郷)に苦しみ涙を流した由来が記されている。江戸時代最大規模といわれた伝馬騒動(百姓一揆)の発祥地だったのです。明和元年(1764)ですから、今から249年前のことです。
一揆勢は中山道を江戸に向け、暴動しながら南下、本庄・深谷・熊谷・鴻巣宿地区の農民も加わり、一揆勢20万人となり、破竹の勢いで江戸へ。震え上がった江戸幕府は急ぎ、農民達から敬愛されている関東郡代伊奈忠宥の家臣を桶川宿へ派遣し、一揆勢は伊奈家臣の言葉なら信用出来ると判断し、江戸の強訴を取りやめた。桶川宿本陣で治まりしたが、西側農民の一揆勢は、帰路、川田谷地区での大暴動(高橋仁左衛門家襲撃と六阿弥陀仏)をおこなった。結果的に、多くの犠牲者を出して終結したことを想い、石碑の前で自然に手を合わせてしまっていた。
左側には“浅間山古墳”があり、木が欝叢と茂る小高い丘は横穴式石室を持つ円墳である。古墳の上には浅間神社の社が建つ。参拝して北へ、間も無く、神保原駅前通りを北に進むと、神保原1丁目交差点で、道は直角(桝形)に左折100m程東で、17号バイパスと交差します。通過して、北東へと進みます。


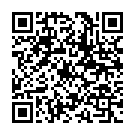
コメントを書こう!