中山道ぶらり歩き旅Ⅵ ~深谷宿から本庄宿~
暫らくして右手に金窪神社・金窪城址公園があるというので見聞に寄る。金窪神社は、毎年10月に奉納される、獅子舞は「雨乞い獅子」として知られるとのこと。奥手に「史跡金窪館跡」の石碑が建つ。この館は神流川合戦で滝川軍によって焼け落ちたという、城址公園を後にして、中山道へ戻り北へと歩く。
金久保という地名が出て左側に“陽雲寺”という有名な寺があるというので寄る。20m程奥まったところにあった。見聞して見ると武田信玄の妻である“陽雲院の菩提寺”という。天文9年(1540)の創建という。多数の文化財を保管している。新田義貞家臣・畑時能供養祠もあった。
石囲いの陽雲院の墓を参拝して、中山道へ戻り北へと賀美小を過ぎ、勅使河原地区に入ると道は西に蛇行する。その右手に白い土蔵と小社が見えて、脇には一里塚の石が建ち、周辺には古い家並みが続く。少し進むと車の騒音が激しいと思ったら17号との合流地点でした。神流川橋が身近に現れます。下を流れる川が神流川、ようやく、武蔵と上野と国境地帯に到着しました。
橋上に行く前に、17号信号を横切り、JR高崎線の下を潜った先に“大光寺”というお寺が、あるというので見聞に、参道に立つと立派な伽藍が並んでいる。左手に“見透燈籠”があり、確認すると文化12年(1815)本庄宿の豪商戸谷半兵衛が神流川を越す旅人のために建立したという燈籠がその役目を終えて、境内の一角に静かに旅人を迎えてくれている。見聞して大光寺を出ます。現在の埼玉県と群馬県の境まで確認して来ます。
17号へ戻り、神流川橋を渡り「神流川古戦場跡碑」を眺める武蔵と上野の国境線の河川敷で天正10年(1582)に滝川一益と北条氏直が川を隔てて戦った古戦場である。案内版を読み終え、深谷宿から本庄宿のぶらり歩き旅は終了します。次回は、上野国(群馬県)新町宿~倉賀野宿~高崎宿となります。


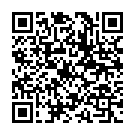
コメントを書こう!